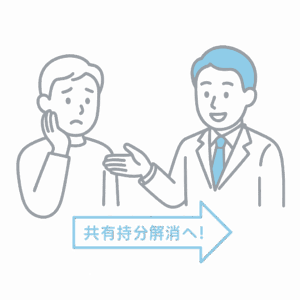共有持分とは?不動産を共有するリスクと解消方法を徹底解説
共有持分とは?不動産を共有するリスクと解消方法を徹底解説
「相続で兄弟と土地を分け合った」「実家を親族と共有している」
このような不動産の共有名義は珍しくありません。
しかし実際には、共有名義の不動産(共有持分)はトラブルの温床になりやすく、放置すれば資産ではなく負担になってしまいます。
この記事では、共有持分の基本からリスク、解消方法、実際の事例、そしてよくある質問までを徹底解説します。
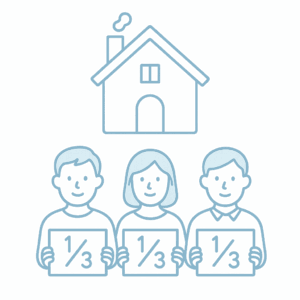
共有持分とは?
不動産の「所有権」を複数人で分け合って持つことを、共有持分と言います。
共有持分が生まれる代表的なケース
相続で兄弟姉妹が土地を分け合う
離婚時の財産分与で夫婦が半分ずつ持つ
投資目的で複数人が共同購入する
例:土地を3人で相続した場合、それぞれが3分の1ずつ所有権を持つ状態。このとき各人が持っている割合を「共有持分」と呼びます。
一見公平に思える共有ですが、実は利用や管理に大きな制限があり、トラブルの原因となりやすいのです。
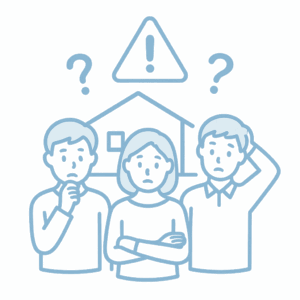
共有持分を所有するリスク
1. 勝手に売却・変更できない
不動産を大規模に修繕したり、全体を売却したりするには共有者全員の同意が必要です。
1人でも反対すれば進められません。
→ 【事例】雨漏りが発生して修繕が必要だったが、1人が費用負担を拒否し建物の劣化が進行。
2. 管理方針が決まらない
「短期賃貸」「外壁修繕」などの管理行為は過半数の持分が必要です。
2分の1では過半数に届かないため、しばしば合意ができません。
3. 知らない第三者が共有者になるリスク
共有者は自分の持分を自由に売却できます。
その結果、まったく知らない第三者と突然共有関係になることも。
4. 分割請求のリスク
民法では共有者はいつでも「共有物分割請求」ができます。
最悪の場合、裁判で競売にかけられ、市場価格より安く処分されることも。
5. 相続でさらに複雑化
1/2の持分がさらに子ども3人に相続されれば、1/6ずつに細分化。
人数が増えるほど合意形成は困難になります。
6. 売却価格が安い
有持分だけを売却する場合、市場価格の1/2〜1/3程度まで下がるのが一般的です。
また共有持分のみで取り扱いを行う不動産会社も多くはなく、適正な査定結果を得られないご相談も多くいただきます。
共有持分を放置するとどうなる?
賃貸収益を得たい → 共有者が同意せず進まない
融資を受けたい → 他の共有者の承諾がなければ担保にできない
修繕が進まない → 建物の価値が下がり続ける
結果的に、共有持分は「資産」ではなく「負担」に変わるリスクがあります。
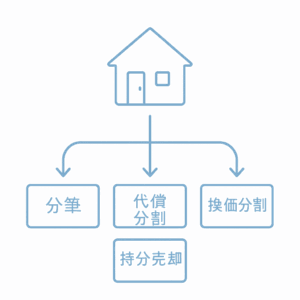
共有持分の解消方法
1. 土地の分筆(現物分割)
土地を物理的に分け、それぞれが単独所有者になる方法。
→ 広い土地なら有効だが、狭小地や建物付きでは現実的でないことも多い。
2. 代償分割(持分買い取り)
共有者の1人が不動産全体を取得し、他の共有者に現金で代償を支払う方法。
公平だが、買い取る資金力が必要。
3. 換価分割(全体売却)
不動産全体を売却し、売却代金を分配する方法。
ただし共有者の誰かが反対すれば実行できない。
4. 遺産分割協議で防ぐ
相続時に「誰が取得するか」を決めておけば、共有自体を避けられる。
5. 自分の持分を売却
他の共有者に売却
第三者や専門業者に売却
持分売却はもっとも現実的でスピーディーな解決策。
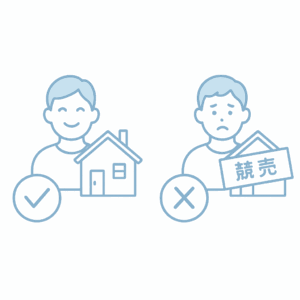
共有持分の事例紹介
成功例①:専門業者に売却して即現金化
兄弟3人で1/3ずつ共有していた土地。
合意形成が困難だったため、1人が専門業者に持分売却。
→ 数日で現金化し、トラブルから解放。
成功例②:兄弟間で代償分割
兄が全体を取得し、弟に現金を支払う形で合意。
→ 不動産を維持しつつ、相続トラブルを回避。
失敗例:放置して競売に
兄弟間で合意できず裁判に発展。
→ 裁判所が競売を命じ、市場価格の7割程度で売却。
全員が不満を抱える結果に。
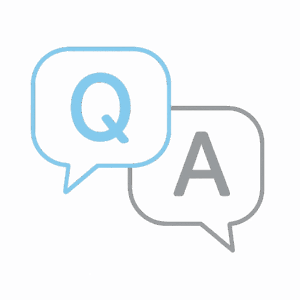
FAQ(よくある質問)
共有持分だけを売ることは可能ですか?
はい、可能です。ただし市場より安い価格になる傾向があります。他の共有者に知られずに売却できますか?
知られずに売却は可能です。、登記上は公開情報のため、売却後に知られる可能性は高いです。専門業者と一般の不動産会社の違いは?
一般会社は取り扱いを避けることが多いですが、専門業者なら即時対応可能です。税金はかかりますか?
売却益が出た場合は譲渡所得税が課税される可能性があります。持分を放棄することはできますか?
可能ですが、他の共有者に迷惑をかける形になり、現実的な解決にならない場合もあります。競売になるとどうなりますか?
市場価格より安く売却され、思わぬ損失を被ることがあります。相続時に避ける方法は?
遺産分割協議で「誰が取得するか」を事前に決めることが最も有効です。